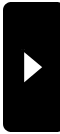› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2012年01月
› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 2012年01月2012年01月21日
プロジェクトKみんなdeトーク

プロジェクトK『みんなdeトーク』を草津駅西口のまちづくりセンター、フェリエ南草津で開催致しました。
お忙しい中にも、ご参加いただきました皆様におかれましては、草津のまちづくりについて、熱心にご討議賜りありがとうございました。
プロジェクトKの活動報告のあと、『みんなで条例をつくろう』というテーマで、現在、提案されている計画案、条例案に対して、パブリックコメントを提出しようということで、グループワークをいたしました。

今回は、景観計画案、交通安全計画案などについて、説明し、グループに分かれていただきました。みなさん最初は、「こんなん急に言われても•••」「ちょっと待ってなあ•••」って感じでしたが、意見が少し出てくると、言葉が出てくるようになり、みなさんで話し合うようになっていきました。短い時間でしたが、たくさんの意見が出て、結構、グループごとで盛り上がっていました。最後に、グループごとに発表いただき、みなさんで市に提出することになりました。
みなさんから、「こんなことみんなで話をすることあんまりせえへんし、おもしろかったわ」とか「もっとこんなことも話し合ったらいいんちゃうの?」など今後も、こういう機会をしてほしいという声をいただきました。
みんなで話し合うことが、まちづくりの第一歩ですよね。
計画や条例をつくることが目的ではありません。
それをどう暮らしの中で、活かされるか?どう活用してほうが大切です。
これから行政がどうしていくか?注目しましょう!
みんなでまちづくり、しっかりやっていきましょう!
Posted by 伊吹達郎 at
23:40
│Comments(0)
2012年01月20日
遅い交通の再生

モータリゼーションの進展や利用ニーズの多様化を要因とした自動車交通の増大によ る環境問題や、今後の少子高齢化社会に対応するため、コンパクトなまちづくりとそれを支える、総合的な交通戦略計画が求められています。
市内中心部で「歩いて暮らせる街づくり」構想を策定し、住民参加の まちづくりとして『坂の上の雲まちづくり』を進めている松山市へ行政視察に行きました。
交通体系において、自動車交通主体から公共交通や自転車•歩行者主体への転換へ、いわゆる『遅い交通』の再生が全国で進められつつあります。また、歩くことは、健康増進と医療費の節約を生み、健康、医療、福祉の観点からもまちづくりは転換期にあります。
松山市においては、市内中心部は最大の商店街、官庁街を抱える地区で、戦災復興の区画整理により比較的 広幅員の道路を有していることから、既存の道路機能を見直し、道路幅員を再配分し、車 道を削減することにより自動車交通を抑制し、歩行者、自転車空間を拡大する方策を採用しています。松山最大の商店街である大街道に隣接し松山城へのエントランスでもあるロープウ ェイ通りでは、幅員 12m の中で、2 車線 7m の車道と 2.5m の両歩道を有する道路を、5m の 1 車線の車道(路肩 1.0m を自転車道)、3.5m の両歩道に再配分し、電線類地中化やファ サード整備、レンガ敷の歩道や趣のある照明を採用するなどの景観整備を行うとともに、道路線形を設計速度 30km の蛇行形状とすることで通過交通を抑制し、歩行者自転車優先 の道路整備を行ない、歩行者の増加や商店街の活性化に成功しています。
観光地である道後温泉周辺においても、写真のように道路の付替えによる歩行者専用空間の創出や一 方通行により車線数を減らし、駅前からの観光客の導線を確保と景観整備を実施し、活性化に成功しています。
草津市においては、しばらくは人口増加しますが、そのうちにしっかりした基盤と整えていかないとなりません。中心市街地活性化も急務のひとつで、旧草津川跡地を含めて、公共交通の整備と遅い交通の再生を進めていかなければなりません。そこで、人口減少、少子高齢化を迎えるにあたり、今までと異なるまちづくりの視点で、健康、医療、福祉の分野と連携し、道路空間の再配分や自転車•歩行者ネットワークの形成、交通需要マネジメント施策などが必要だと考えます。
Posted by 伊吹達郎 at
23:13
│Comments(0)
2012年01月19日
水の都ひろしま『水辺オープンカフェ』視察

産業建設常任委員会の行政視察で広島市を訪れ、都市活性化局観光交流部の皆さんから水の都ひろしまの推進(水辺のオープンカフェ)のお話をいただき、意見交換し、現地視察も行いました。
広島市は瀬戸内海に面し、中心部を6本の川が流れる「水の都」であり、美しい水辺に恵まれています。その魅力を生かして、京橋川や元安川の河岸緑地において、水辺に新たな魅力を創り出すため、民間のノウハウや活力を導入した「水辺のオープンカフェ」を実施されています。
現在、京橋川沿いの河岸緑地では7店舗、元安川沿いでは1 店舗が営業中であり、多くの市民や来訪者に憩いの場、交流の場を提供するとともに、潤いと安らぎを感じる風景を創り出しています。
中でも、平成17年10月に開業した京橋川オープンカフェ(独立店舗型)は、河川空間で民間事業者による常設店舗を設置した全国初の取組であり、多くの賞を受賞するなど、河川空間の新しい利活用モデルとして、その先見性や革新性、汎用性などが高く評価されています。
この活動は、単に水辺の親水性の向上という視点だけでなく、公共空間を都市資源ととらえ、活性化することによりにぎわいの場をつくりだし、持続可能な管理を行おうとするエリアマネジメントの取り込みであり、旧草津川跡地利用などを含めた中心市街地活性化に活かして行きたいと考えます。
Posted by 伊吹達郎 at
23:39
│Comments(0)
2012年01月18日
草津ブランド
匠の技を見せていただきました。
超薄の球形に仕上げた焼き物にいくつもの丸い穴があいている。
何だろう?
鉛筆立て?
珊瑚?
ろくろでこんなに薄く球形に仕上げる技術はもちろんのこと、
計算しつくした穴あけ。
花立て。
驚きました。剣山やオアシスなどお花いけは結構難しいが、
これを使うと、あらゆる角度からお花をいけられるらしいです。
お花いけをもっと楽しく、身近にと考えられ、特許庁意匠登録されました。
使い方はいろいろでしょう!
まだ名前もついていないようです。
年末、みなくさまつりやデパートで人気となり、(1500〜1800円くらい)
かなり売れたそうです。
草津で窯があり、草津の焼き物です。
86年に開窯した淡海陶芸研究所。97年には草津市から『草津焼』として第1期の指定ブランドを受けています。
お問い合わせは
淡海陶芸研究所『草津焼』
http://ohmitogei.com
077-563-5934
ただいま、草津の湖岸にコハクチョウが7羽、飛来してきています。
今しかご覧になることができません。
朝8時ごろがよいかもしれません。
場所は草津駅西口からまっすぐ湖岸道路まで出て、右折し、北へむかった駐車場近辺です。
ボランティアのかたにお世話いただいています。
毎日、ありがとうございます!
滋賀県にも住んでいた伊達選手がエアKの錦織選手と混合ダブルスに出場するそうです。こちらも注目ですね!
Posted by 伊吹達郎 at
23:41
│Comments(0)
2012年01月17日
1.17
阪神•淡路大震災から17年。
そのとき私は、30才でした。
年末の土山マラソンの出場し、疲労しているところへ会社でサッカーチームをつくって初めて、草津市の市民大会での試合で
ひざのじん帯切断してしまい、ギブスをまいて1ヶ月。
1月17日、その日から手術のため入院予定でした。
その朝、自分では起きれないけど目は覚めていました。
ゴロゴロと予震を感じ、地震かなと思った、次の瞬間、強く叩き付けるような
揺れを、当時住んでいたエイスクエア横の4F建ての古いアヤハの社宅を襲いました。
思わずとなり寝ていたまだ赤ちゃんだった長男を守ろうと覆いかぶさりました。
揺れはしばらくすると止まりましたが、その恐怖感は今でも忘れられません。
後から考えると、自分では動けないはずなのに、
なぜか動けていて、痛みも何もありませんでした。
それ以上の何かが働いたのでしょうね?
我が家の被害は、食器が少し破損した程度でしたが、テレビをつけて徐々に被害が明らかになっていく•••
6434の尊い命が一瞬の間に亡くなりました。
改めて、心からご冥福をお祈り致します。
1.17
残された我々が出来ることをしっかりしていかなければなりません。
未来の子どもたちのためにも、素晴らしいまちづくりを!
そのとき私は、30才でした。
年末の土山マラソンの出場し、疲労しているところへ会社でサッカーチームをつくって初めて、草津市の市民大会での試合で
ひざのじん帯切断してしまい、ギブスをまいて1ヶ月。
1月17日、その日から手術のため入院予定でした。
その朝、自分では起きれないけど目は覚めていました。
ゴロゴロと予震を感じ、地震かなと思った、次の瞬間、強く叩き付けるような
揺れを、当時住んでいたエイスクエア横の4F建ての古いアヤハの社宅を襲いました。
思わずとなり寝ていたまだ赤ちゃんだった長男を守ろうと覆いかぶさりました。
揺れはしばらくすると止まりましたが、その恐怖感は今でも忘れられません。
後から考えると、自分では動けないはずなのに、
なぜか動けていて、痛みも何もありませんでした。
それ以上の何かが働いたのでしょうね?
我が家の被害は、食器が少し破損した程度でしたが、テレビをつけて徐々に被害が明らかになっていく•••
6434の尊い命が一瞬の間に亡くなりました。
改めて、心からご冥福をお祈り致します。
1.17
残された我々が出来ることをしっかりしていかなければなりません。
未来の子どもたちのためにも、素晴らしいまちづくりを!
Posted by 伊吹達郎 at
23:27
│Comments(0)