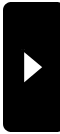› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 議場で議員研修会
› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 議場で議員研修会2012年02月02日
議場で議員研修会

大津市の議場において、大津市議会主催の議員研修があり、参加してまいりました。講師はLORC議員政策力フォーラムでお世話になっている土山希美枝・龍谷大学政策学部准教授 です。
今日のテーマは『「議論する議会」への議会改革〜議会と市民との新しい関係のために』でした。
政策は現在からめざす未来にたどり着くためのシカケ。それを多様なひとが多様に展開しているところが面白い。われわれはそれぞれ違う理念や価値観や立場や利害を持ち社会をつくっています。どんな未来をめざすのか?それにどんなシカケが必要なのか?そこに「あらかじめ分かっている正解」はありません。おそらく今までの教育では、いろいろな試験など「あらかじめ分かっている正解」を求めることばかりしているので、それについては得意です。いろんな意見や事情や情報をぶつけあって「これ、やってみようか」という合意にたどりつく。成功でも失敗でも、その結果としてちょっと未来がつくられて行く。のりこえるべきは戦後体制ではなく高度成長期構造で『持続可能な社会のための「政策・制度ネットワーク」である公共政策のありかた』を語っていただきました。
なぜ議会基本条例が流行るのか?
年々議会条例は増え続け、2011年3月では207自治体に制定され、あと150自治体が制定をめざしていると言われています。原因は地方議会への攻撃で、こんにちの市民にとその集合体である社会にとって「議会」とは何ものなのか?そこで再設定の必要にさらされているからなのです。
地方の政府は長と議会で構成されていて、そのミッションは、長と議会のチェックアンドバランシズで政策提案•策定と適正な行政運営の監査を通じて、「有限資源の有効配分」のやり方を決定することです。社会にある多様な意見を意思形成過程で可視化させられるのは議会だけで、「公開のヒロバで議論し決定する」という構造特性をもっているので、「議論」をともなう決定の重要性があり、また、長の暴走を止めるのも議会しかできません。
議会改革の方向性としては、議会の本質的機能「議論」「討議」することの充実、回復のためのシクミと実践で、その機能を「見える化」し、主権者である「市民のアクセス」を拡充するための議会なりの市民参加•情報公開の手法もありうるのでは?
大矢野先生、土山先生、大津市議会のみなさんありがとうございました。
Posted by 伊吹達郎 at 23:51│Comments(0)