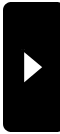› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 草津ハスの群生地調査結果
› 伊吹達郎の活動日記『2222人との握手』 › 草津ハスの群生地調査結果2017年05月31日
草津ハスの群生地調査結果
昨年、突然のハスの消失。
あれほど、湖面を彩っていたハスの花が姿を消しました。草津市はその原因を追求すべく、調査を依頼していましたが、結果も、これも突然NHKニュースで発表されました。ニュースを見てびっくりです。
「人の手では無理?!」ヨシは良くてハスはだめ?!
これから、自然と対話し、どうして行くのが良いのか、考えていかなければならないと思います。
(NHKHPより)
全国有数のハスの群生地として知られてきた滋賀県草津市のびわ湖で、去年、ハスがほとんど育たなかった原因について、市から依頼を受けた専門家が、ハスの生育に欠かせない粘土が湖の底からなくなっていて、人の力でハスの群生地を取り戻すのは難しいとする報告書をまとめたことが分かりました。
びわ湖南部の滋賀県草津市の烏丸半島の周辺一帯は、35年ほど前からハスが群生し、おととしは、13アールほどにハスが育つ全国有数の群生地として知られてきましたが、去年はほとんど育たず、調査した草津市や滋賀県は、大量に枯れたハスが湖の底に堆積して土壌が酸欠状態となったことが原因としていました。
一方、群生地を再生させる手だてがないか探るため、草津市は、びわ湖の環境に詳しく、20年前、同じ地点で水質や土壌を調査した、滋賀県立大学の小林圭介名誉教授に調査を依頼しました。
その結果、以前は湖の底を覆い、ハスの地下茎の生育に必要な粒の細かい粘土がほとんど確認出来ず、砂地に変わっていたことが新たにわかりました。
また、水中のメタンガスが20年前と比べて、多いところで8倍、少ないところでも5倍に増えていることも確認され、このガスがハスの成長を妨げた可能性があるということです。
ハスに代わって砂地を好むヨシの群落が大きく拡大していて、小林名誉教授は、人の力でハスの生育環境を復元し、群生地を取り戻すのは難しいとする報告書をとりまとめました。
小林名誉教授は「人が手を加えると、水質の悪化や生態系の撹乱を起こしかねない。あくまで基本的には自然の力に任せ、試験的な取り組みを少しずつ進めるべきだ」と話しています。
【これまでの調査の経緯】
滋賀県草津市のびわ湖では、例年、6月下旬ごろから湖面を埋め尽くすようにハスが育ち、全国各地から観光客が訪れる名所となっていました。
ハスの群生が見られるようになったのは35年ほど前からで、おととしは群生地が、30年前の2倍にあたる13アールまで広がりました。
ところが、去年は7月を過ぎてもハスの姿がほとんど見られず、草津市や滋賀県は外部の専門家の意見を聞いたり、やはりハスが育たなくなった岐阜県海津市の国営公園と連携したりして、原因の調査を進めました。
当初は、▼カメやザリガニによる食害、▼細菌による病気、▼湖の底の土壌の環境の悪化、それに、▼ハスの寿命による老化といった複数の要因が考えられていましたが、草津市は去年10月、湖底に堆積した枯れたハスが土壌を酸欠状態にしたことが原因だったとする調査結果をまとめていました。
【観光関係者は危機感】
草津市では、民間の業者が15年前からびわ湖のハスの群生地の周辺を船で巡るツアー「ハスクルージング」を行っています。
このツアーは、おととしはおよそ1300人がハスを観賞しました。
しかし、ハスの姿がほとんど見られなくなった去年はキャンセルが相次ぎ、利用客がわずか80人まで落ち込みました。
こうした状況を受けて、運営会社では別のツアーを検討しているということです。
ツアー運営会社の畑源代表は、「夏の仕事の柱なので大打撃です。
今後は“ハス”という名前を変更して営業するしかない。早く元に戻ってほしい」と話していました。
また、群生地の近くにある草津市の「水生植物公園みずの森」では、去年7月と8月の来園者が前の年の60%にとどまりました。
このため、ことしは7月下旬に行われる恒例の「ハス祭り」を中止し、別のイベントを実施するということです。
竹中勉副公園長は、「ハスがなくなったことを受けてイベントを変更しますが、園内ではハスを育てているのでぜひ見に来てもらいたい」と話しています。
ハスの群生を夏の観光の呼び物にしようと取り組んでいた草津市商工観光労政課の中村秀史課長は、今回の調査結果を受けて、「ハスが復活しないと市の観光に大きな影響を与える。別の資源で観光客の呼び込みを進めなくてはならない」と危機感を表していました。
【訪れた人“早期の回復を”】
ハスの再生のメドが立たないことについて、群生地を訪れた人からは早期の回復を望む声が相次ぎました。
毎年、群生地に写真を撮りに訪れるという滋賀県栗東市の60代の男性は、「改めて群生地を眺めてみると景色が一変している。ハスの再生が難しいと聞き、とても残念だ。きれいな姿がよみがえってほしい」と話していました。
大阪・東大阪市から釣りに訪れていた30代の男性は、「初めて来ましたが、ここにハスがあったなんて思いもよらなかった。ハスが復活すればまた来たい」と話していました。
あれほど、湖面を彩っていたハスの花が姿を消しました。草津市はその原因を追求すべく、調査を依頼していましたが、結果も、これも突然NHKニュースで発表されました。ニュースを見てびっくりです。
「人の手では無理?!」ヨシは良くてハスはだめ?!
これから、自然と対話し、どうして行くのが良いのか、考えていかなければならないと思います。
(NHKHPより)
全国有数のハスの群生地として知られてきた滋賀県草津市のびわ湖で、去年、ハスがほとんど育たなかった原因について、市から依頼を受けた専門家が、ハスの生育に欠かせない粘土が湖の底からなくなっていて、人の力でハスの群生地を取り戻すのは難しいとする報告書をまとめたことが分かりました。
びわ湖南部の滋賀県草津市の烏丸半島の周辺一帯は、35年ほど前からハスが群生し、おととしは、13アールほどにハスが育つ全国有数の群生地として知られてきましたが、去年はほとんど育たず、調査した草津市や滋賀県は、大量に枯れたハスが湖の底に堆積して土壌が酸欠状態となったことが原因としていました。
一方、群生地を再生させる手だてがないか探るため、草津市は、びわ湖の環境に詳しく、20年前、同じ地点で水質や土壌を調査した、滋賀県立大学の小林圭介名誉教授に調査を依頼しました。
その結果、以前は湖の底を覆い、ハスの地下茎の生育に必要な粒の細かい粘土がほとんど確認出来ず、砂地に変わっていたことが新たにわかりました。
また、水中のメタンガスが20年前と比べて、多いところで8倍、少ないところでも5倍に増えていることも確認され、このガスがハスの成長を妨げた可能性があるということです。
ハスに代わって砂地を好むヨシの群落が大きく拡大していて、小林名誉教授は、人の力でハスの生育環境を復元し、群生地を取り戻すのは難しいとする報告書をとりまとめました。
小林名誉教授は「人が手を加えると、水質の悪化や生態系の撹乱を起こしかねない。あくまで基本的には自然の力に任せ、試験的な取り組みを少しずつ進めるべきだ」と話しています。
【これまでの調査の経緯】
滋賀県草津市のびわ湖では、例年、6月下旬ごろから湖面を埋め尽くすようにハスが育ち、全国各地から観光客が訪れる名所となっていました。
ハスの群生が見られるようになったのは35年ほど前からで、おととしは群生地が、30年前の2倍にあたる13アールまで広がりました。
ところが、去年は7月を過ぎてもハスの姿がほとんど見られず、草津市や滋賀県は外部の専門家の意見を聞いたり、やはりハスが育たなくなった岐阜県海津市の国営公園と連携したりして、原因の調査を進めました。
当初は、▼カメやザリガニによる食害、▼細菌による病気、▼湖の底の土壌の環境の悪化、それに、▼ハスの寿命による老化といった複数の要因が考えられていましたが、草津市は去年10月、湖底に堆積した枯れたハスが土壌を酸欠状態にしたことが原因だったとする調査結果をまとめていました。
【観光関係者は危機感】
草津市では、民間の業者が15年前からびわ湖のハスの群生地の周辺を船で巡るツアー「ハスクルージング」を行っています。
このツアーは、おととしはおよそ1300人がハスを観賞しました。
しかし、ハスの姿がほとんど見られなくなった去年はキャンセルが相次ぎ、利用客がわずか80人まで落ち込みました。
こうした状況を受けて、運営会社では別のツアーを検討しているということです。
ツアー運営会社の畑源代表は、「夏の仕事の柱なので大打撃です。
今後は“ハス”という名前を変更して営業するしかない。早く元に戻ってほしい」と話していました。
また、群生地の近くにある草津市の「水生植物公園みずの森」では、去年7月と8月の来園者が前の年の60%にとどまりました。
このため、ことしは7月下旬に行われる恒例の「ハス祭り」を中止し、別のイベントを実施するということです。
竹中勉副公園長は、「ハスがなくなったことを受けてイベントを変更しますが、園内ではハスを育てているのでぜひ見に来てもらいたい」と話しています。
ハスの群生を夏の観光の呼び物にしようと取り組んでいた草津市商工観光労政課の中村秀史課長は、今回の調査結果を受けて、「ハスが復活しないと市の観光に大きな影響を与える。別の資源で観光客の呼び込みを進めなくてはならない」と危機感を表していました。
【訪れた人“早期の回復を”】
ハスの再生のメドが立たないことについて、群生地を訪れた人からは早期の回復を望む声が相次ぎました。
毎年、群生地に写真を撮りに訪れるという滋賀県栗東市の60代の男性は、「改めて群生地を眺めてみると景色が一変している。ハスの再生が難しいと聞き、とても残念だ。きれいな姿がよみがえってほしい」と話していました。
大阪・東大阪市から釣りに訪れていた30代の男性は、「初めて来ましたが、ここにハスがあったなんて思いもよらなかった。ハスが復活すればまた来たい」と話していました。
Posted by 伊吹達郎 at 23:19│Comments(0)